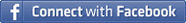セルバンテスやシェクスピヤでは、狂気はつねに、それには救いがないという点で極端な位置をしめている。狂気はいかなるものによっても、真理や理性につれもどされない。狂気の通路の先には、裂け目、そこからさらに死しか存在しない。…狂気が…突然、知恵を示したことは、「彼が何か新しい狂気にとらえられた」ことにほかならない…結局、死じたいによってしか一刀両断に解決されないものなのである。狂気の消滅は、最期が近づいていることと同じである。…しかしごく速やかに、狂気は…資の領域から離れる。十七世紀初頭の文学では、小説や演劇の作品構造の仕組みのなかに移されてしまった狂気は、真理を表明したり理性を穏やかに復帰させる場合の口実の役目をはたす。その理由は、狂気はもはや、その悲劇的現実において、あの世へ狂気を導く絶対的な悲痛さにおいて考察されずに、ただ単に狂気のもつ幻想の皮肉を通して把握されているからだ。狂気は現実の懲罰ではなく、懲罰の写し、従って見せかけであり、犯罪の仮象や死の幻影としか結びつくことができない。…つまり、狂気が懲罰や絶望となるのは、錯誤の次元においてでしかないのである。(p.54-56)
--出典:
狂気の歴史―古典主義時代における