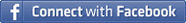1948年生まれの著名な<言語>派社会学者が1988年に刊行した、構造主義思想の入門書(1996年18刷)。構造主義とは、西欧文明中心の近代を批判し、現代思想の時代を切り開いた思想であり、通常ユダヤ系フランス人類学者レヴィ=ストロースの名と結び付いて論じられる。したがって著者は、主としてレヴィ=ストロースの思想史的背景を探ることにより、構造主義の核心に迫ろうとする。レヴィ=ストロースは、機能主義人類学の限界を乗り越えるため、ソシュール一般言語学、ヤーコブソン音韻論の二項対立原理、モースの贈与・交換論を親族(婚姻関係)・神話研究に応用する。彼の本領は、神話研究の方で発揮されたようで、同一系統神話同士を比較し、神話の筋を無視して(主体・テキストの解体、歴史の無視)神話素に解体し、それらを貫く対立軸を発見し、隠された深層構造を把握するという手法(テキストの「読み方」の前景化)だった。その際、彼の構造理解は、人的な面で数学者集団ブルバキの影響下にあることが確認され得、したがって構造は変換とセットで考えられるべきであり、視点(主体)の差異が無視されること(遠近法の解体)で、浮かび上がる仕掛けになっている。それは真理の相対化(「制度」化)の過程でもあり、西欧の思想と「未開」の神話の間に、本質的な差異は無いことになる。著者はこのように構造主義の思想史的意義をまとめた後、その他の代表的な現代思想家を一瞥し、日本においてはポスト構造主義よりもまず自前のモダニズムの方が重要であるという、それなりに妥当な持論を主張している。一応構造主義が分かったつもりにはなれる本だと思うが(人類の最深層の思考の共通性を取り出すための思想と言って良いのだろうか)、著者も指摘するように、この方法が本当に「客観的な」方法かどうかはやはり疑問だ。
--出典:
はじめての構造主義 (講談社現代新書)