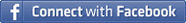[2]狂気は、理性の諸形態そのものの一つとなる。狂気は理性の一部になって、その秘密の力の一つ、あるいは理性のあらわれの契機の一つ、あるいは理性が自分を自覚する逆説的な形式の一つを構成する。…真の理性は、痴愚とのどんな係わり合いをも免れるわけにはいかない。それどころか、それは痴愚によって示される道をえらばねばならないのである。…この道がゆきつく先には、どんな最終的な知恵もないとしても、この道が約束する至福の城が実は蜃気楼と新たな痴愚にすぎないとしても、この道はそれ自体としては知恵へいたる道なのである。まさしく、それこそ痴愚へいたる道であることを心得つつそれをたどっていく場合には。…この痴愚(狂気)をどこに位置づけるべきかというと、理性じたいのなかに、理性の諸形態の一つとして、恐らくは理性の支えの一つとして位置づけるほかあるまい。…「狂気の混ざらぬような偉大な精神は存在しない。…そういう意味で、賢者ともっとも優れた詩人たちは気がふれたり、時には激昂することを容認したのであった」…しだいに狂気は無力にされ、…理性によって取り囲まれている狂気は、理性のなかに、いわば受け入れられて植え込まれたようになる。…理性に内在的な狂気の発見、つぎに、そのことに由来する二重性…。この二重性とは、一方では、理性に固有な狂気を拒否し、それを排除しつつもそれを倍加し、その倍加によって、狂気のなかのもっとも単純でもっとも閉じられもっとも無媒介な狂気に陥っている《狂った狂気》であり、他方では、理性のもつ狂気を受け入れ、それに耳をかたむけ、その市民権を容認し、その激しい力の侵入をそのままにしている《おとなしい狂気》である。…今や、狂気の真理はもはや理性の勝利およびその決定的な制圧とまったく同じ…。狂気の真理とは、狂気が理性にとって内的であり、いっそうよく自分を確保するために理性の一形姿・一つの力・いわば一つの必要である、という点にある。(p.49-52)
--出典:
狂気の歴史―古典主義時代における